ふるさと納税 確定申告をすると住民税はどうなるの?詳しく教えて!
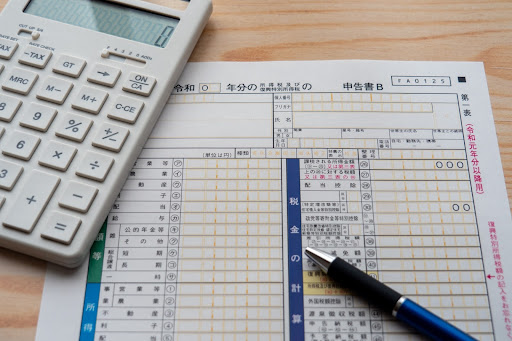
ふるさと納税のメリットは寄附をすることで寄附金から2,000円を差し引いた分が税金の控除対象になり、さらに返礼品を受け取れることにあります。確定申告で控除されるのは所得税なのでしょうか?住民税なのでしょうか?この記事では確定申告をしたときの控除の仕組みから、注意点などを詳しく解説していきます。
ふるさと納税をした人は確定申告をすべきか?

通常は自営業の方や不動産収入がある方などが対象となり、一つの企業から給与を受け取っている給与所得者は確定申告をする必要はありません。しかし、税込みで年間2,000万円超の給与・収入があった方、医療費控除や寄附金控除がある方、初めて住宅ローン控除を受ける方は、給与所得者であっても確定申告が必要です。したがってふるさと納税の寄附金も確定申告をすることで控除される仕組みになっています。返礼品のためにふるさと納税をやっている方にとって寄附金控除を受けないということは、寄附金額の約3割にあたる返礼品を3倍の金額で購入していることになってしまいます。忘れずに確定申告をしましょう。確定申告は原則として寄附した翌年の3月15日までに終わらせる必要があります。ただし、全員が確定申告をすべきというわけではなく、ワンストップ特例を申請する方は不要です。
ふるさと納税をした人が確定申告すると住民税は安くなるか?
確定申告をすれば寄附した翌年の住民税は安いです。ただし2,000円を除く寄附金額=控除額であるため、税金を前払いしていることと同じです。納税者の実質出費は2,000円を除いて変わらず節税効果はありませんが、寄附金を現金ではなくクレジットカード決済等で支払えるのはメリットでしょう。
下の図は確定申告をした場合の控除について示したものです。ご覧のとおり住民税だけでなく所得税からも控除(還付)されることがわかります。全額住民税から控除されるわけではありません。

引用:総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税のしくみ」
具体的な控除額の計算式は以下のとおりです。
所得税からの控除(①)
(寄附金額 - 2,000円) × 所得税率(所得金額により0~45%) × 復興税率*
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
*復興税率は1.021で2037年末まで2.1%が上乗せされます。
住民税控除(基本分)(②)
(寄附金額 - 2,000円) × 10%
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
住民税控除(特例分)(③)
(寄附金額 - 2,000円) × (100% - 基本分税率10% - 所得税率 × 復興税率)
住民税通知書から「住民税所得割額**」を確認します。控除の対象となるふるさと納税額は、この住民税所得割額の20%が上限です。上限を超えた場合は下記のとおりです。
**住民税所得割額とは課税所得金額の10%です。
(寄附金額 - 2,000円) × 20%
ふるさと納税と確定申告をして住民税が安くならない理由で考えられることとは?
住民税から正しく控除されているかは寄附した翌年の住民税決定通知書で確認できます。
ここでは確定申告をしたのにも関わらず翌年の住民税決定通知書で寄附金分の控除がなかったもしくは満額控除されていなかった場合について説明します。考えられる要因は以下のとおりです。
所得税の還付分は住民税から控除されない
すでに説明したとおり確定申告を選択した時点で、寄附金の満額は住民税から控除されません。所得税からの控除(還付)と住民税からの控除の合計になります。
控除の限度額を超えて寄附をしている
所得によって寄附金(控除)の限度額が決まるふるさと納税で注意しなければならないのは、知らないうちに限度額を超えて寄附を行っていた場合です。限度額を超えた分はすべて自己負担になりますので、その分は控除されません。寄附金限度額の計算式は以下のとおりです。
住民税所得割額 × 20% ÷ (100% - 10% - 所得税率 × 復興税率) + 2,000円
納税者と寄附者の名義が異なる
税金の控除は基本的に所得のある人が税金を過度に支払わないようにしている減税措置です。税金を支払う人と控除が受けられる人は同一でなければいけません。したがって、住民税を納めている人(納税者)と控除を受けるために他の自治体に納税している人(寄附者)も同一でなければ控除は成り立ちません。
ふるさと納税と確定申告の注意点
寄附金受領証明書の保管
確定申告を紙で提出する際は寄附金受領証明書が必要です。寄附をすると後日、寄附した自治体から送られてきます。寄附するたびに発行されるものなので保管しておきましょう。ただし、Webで確定申告をする場合は寄附金受領証明書の提出は不要です。
住宅ローン減税との併用
住宅ローン控除を適用する方は住民税から控除される限度額を考慮する必要があります。住民税から控除される住宅ローン減税の限度額は以下のとおりです。
<2014年4月1日から2021年12月31日までに居住した場合>
- 所得税の住宅ローン減税控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった金額
- 所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じた額(限度額13万6,500円)
この2つのうちいずれか小さい額
<2014年1月1日から3月31日までに居住した場合>
- 所得税の住宅ローン減税控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった金額
- 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じた額(限度額9万7,500円)
この2つのうちいずれか小さい額
ワンストップ特例制度を使えば、ふるさと納税の控除は住民税のみでおこなわれるため、ふるさと納税の控除額のせいで住民税から控除される住宅ローン減税の限度額を超えることはありません。しかし確定申告をすると、ふるさと納税も所得税と住民税から控除されるため、住民税から控除される住宅ローン減税の限度額に注意が必要です。万が一、限度額を超えると、その超えた部分は住宅ローン控除枠を活かしきれなかった分になります。
確定申告のやり方と必要書類
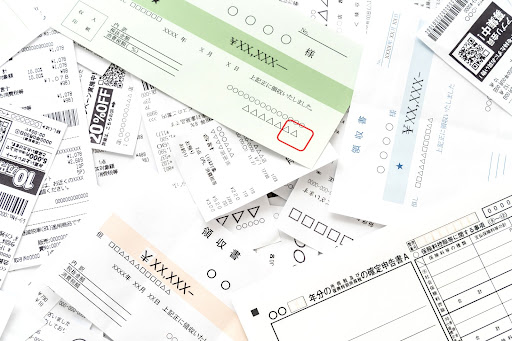
ここでは確定申告をするにはどんな手段があるのか、準備しておくものは何かを解説します。
申告会場で確定申告
- マイナンバーカード(持っていない方は免許証等)
- 寄附金受領証明書
- 源泉徴収票
- 還付金を受け取る口座番号
- 印鑑
デメリットは、証明書等は紙面で提出するため全て保管しておくか無いなら印刷しなければなりません。そして何といってもほとんどの時間は何もしていないことです。足を運ぶのが面倒で平日に時間が取れないからといって休日に行くと大変混雑します。
メリットは、会場に税理士さんがいてサポートしてくれるため申告書類作成に時間はかかりません。
役所で確定申告
- マイナンバーカード(持っていない方は免許証等)
- 寄附金受領証明書
- 源泉徴収票
- 還付金を受け取る口座番号
- 印鑑
デメリットは、証明書等は紙面で提出するため全て保管しておくか無いなら印刷しなければなりません。そして受付が地区ごとになっているがゆえに受付期間や時間が限定的で、平日に休みをとらざるをえない可能性が高いことです。
メリットは、会場に税理士さんがいてサポートしてくれるため申告書類作成に時間はかかりません。その自治体の住民しか来ないのと受付が地区ごとになっていれば申告会場に行くよりは待ち時間が少なくて済みます。
Webで確定申告
- マイナンバーカード
- マイナポータルアプリ
- NFC対応のスマートフォンもしくはカードリーダー&パソコン
- 寄附金受領証明書もしくは記憶している合計金額
- 還付金を受け取る口座番号
デメリットは、マイナポータルでふるさと納税ポータルサイト企業との連携および電子寄附金受領証明書の連携が少々わかりづらいです。
メリットは、家でできることと、証明書等の印刷物の提出が不要なことです。マイナンバーカードとマイナポータルで連携が済んでいれば医療費や寄附金が自動で反映されます。
確定申告とワンストップ特例制度は何が違う?

寄附金控除額で比較するとどちらも変わりはありませんが、控除の仕組みや適用条件が異なります。
確定申告
寄附金控除は所得税の還付および住民税からの控除の合計になります。寄附をする自治体数に制限がありません。
ワンストップ特例制度
寄附金控除は住民税からのみ控除されます。寄附をする自治体数は5つまでです。ただし同一自治体に複数寄附してもカウントは1つとして扱われます。
確定申告不要であることが前提のため、税込みで年間2,000万円超の給与・収入があった方、医療費控除や寄附金控除がある方、初めて住宅ローン控除を受ける方は適用できません。
まとめ
今回は確定申告で寄附金控除を受ける場合についてまとめてみました。
①以下に該当する場合は確定申告をする必要がある
- ワンストップ特例をしない
- 寄附先の自治体数が6つ以上
- 2,000万円超えの収入がある
- 住宅ローン控除が1年目
- 医療費控除がある
②確定申告をすると所得税からの控除(還付)と住民税からの控除になる
いかがでしたでしょうか?ふるさと納税をすることで返礼品を受け取れることは非常にありがたいですが、そもそも税金の控除や適用ルールについてわからずにやるよりはわかっていたほうがいいですよね。うまく活用してふるさと納税を楽しみましょう!




























